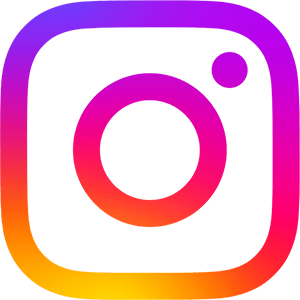教員一覧(2025年度)
保育学科
髙橋 雅人
- 准教授

プロフィール (自己紹介)
私が福祉の道を選択したきっかけは、中学生の時に障がいを持った友人がいたことです。以来、福祉の現場一筋で今に至っています。大学時代、障がい者施設や児童館のボランティアを経験した後に東京都職員として福祉事業に尽力しました。とくに、障がい者施設、児童自立支援施設、児童相談所などでは、現代の多様な課題を抱える利用者や子どもたちとそれに向き合う職員や家族の情熱に触れてきました。これらの経験を学生に伝えることが、私の使命だと思っています。
主な担当科目
- 社会福祉
- 子ども家庭福祉
- 社会的養護Ⅰ、Ⅱ
ゼミナール研究テーマ
子ども学 子どもの理解/社会の理解
現代の子どもを取りまくいじめや虐待、貧困問題などを多角的、かつ、客観的視点で考えてみましょう。問題を抱えている子どもの年齢は一定ではありません。そのため、乳幼児から学齢児童までと幅広い年齢の子どもたちを研究対象とします。自らの子ども時代を振り返りながら、過去から現代、未来に向けて子どもを取りまくあらゆる問題を理解するとともに、子どもにしっかりと向き合い寄り添う技術、保育士のあり方を考察していきましょう。
学生へのメッセージ
保育士は、虐待やいじめに苦しんでいる子どもと直面することも現実です。その現実のなかで、不安を抱え悲しい表情をした子どもにどのように接したいと思いますか?心がけてほしいことは、心を癒す「やさしい笑顔」、慰めと勇気を与える「正しい言葉」、信頼を与える「きれいな身なり」の3つです。湘北短期大学の2年間で、ぜひこの3つを身につけ、不安を抱えた子どもを笑顔に変えていきましょう。そのために私も全力でサポートしていきます。ともに成長しましょう。
その他
【学外活動】
・2021年(R3)
厚木市青少年問題協議会講師:「現代の子どもを取り巻く多様な問題について」
・2023年(R5)
厚木市睦合北地区青少年健全育成会研修講師:「ヤングケアラーについて考える-子どもが子どもでいられるために-」
・2024年(R6)
厚木市青少年問題協議会講師:「ヤングケアラーについて-彼らのSOSを見逃さないために-」
厚木市小中一貫教育推進事業における厚木市立睦合中学校区小中一貫教育研修会研修講師:「さまざまな問題を抱える子どもたちの対応」
厚木市子育て支援者研修会研修講師:「子どもの人権について」
厚木市相川地区青少年健全育成会講師:「ヤングケアラーについて-彼らのSOSを見逃さないために-」
・2021年(R3)
厚木市青少年問題協議会講師:「現代の子どもを取り巻く多様な問題について」
・2023年(R5)
厚木市睦合北地区青少年健全育成会研修講師:「ヤングケアラーについて考える-子どもが子どもでいられるために-」
・2024年(R6)
厚木市青少年問題協議会講師:「ヤングケアラーについて-彼らのSOSを見逃さないために-」
厚木市小中一貫教育推進事業における厚木市立睦合中学校区小中一貫教育研修会研修講師:「さまざまな問題を抱える子どもたちの対応」
厚木市子育て支援者研修会研修講師:「子どもの人権について」
厚木市相川地区青少年健全育成会講師:「ヤングケアラーについて-彼らのSOSを見逃さないために-」
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
| 保有学位 | 修士(文学)佛教大学 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
研究分野 | 社会的養護 社会福祉思想 | ||
| 著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
| ソーシャルワーカー 仕事発見シリーズ㉟(単著) | 平成9年4月 | 実業之日本社 | 本書は、社会福祉関係の仕事を希望する学生へ向けて、障がい者や児童福祉施設で生活を送る子どもたち、その人たちを支える職員の姿を理解してもらう目的で著した一冊である。 | |
| 不登校児童の学習支援について-学習場面における個別支援の具体例-(共著) | 平成26年3月 | 東京都児童相談所一時保護所実務事例検討会 | 児童相談所一時保護所に入所した不登校の児童について、学習場面を通しての支援事例を発表した。内容は、本児童の特性をふまえた個別学習の方法や、学習の成果が一時保護所の日常生活に与えた変化について紹介した。心理職との共同研究。 | |
| 児童相談所一時保護所職員の専門性について(単著) | 平成29年10月 | こども教育宝仙大学紀要vol.9(1) | 本稿は、一時保護所職員の専門性を明確にするため、現場の支援に関連する課題をあげて検討した。その結果、客観的視点、専門家としての人間性、外部との交渉力の3つが強化の条件になると指摘した。 | |
| 児童相談所一時保護所職員の資質の研究-被虐待児童の援助事例を通して-(単著) | 平成30年3月 | こども教育宝仙大学紀要vol.9(2) | 本稿は、一時保護所で生活を送る被虐待児童への援助過程を通して、適切な援助を担う職員の資質について考察した。資質の向上には、自分を知る努力、専門性を強化する研修への参加、倫理観を養うことが必要であり、資質の向上が援助の質を高めると指摘した。 | |
| 児童相談所一時保護所職員に求められる専門性-被虐待児童の支援から-(単著) | 平成31年3月 | こども教育宝仙大学紀要vol.10 | 本稿は、被虐待児童の支援を通して、一時保護所職員に求められる専門性を検討した。その結果、安心を与える職員であること、自立へ向けた過程をともに歩む支援を展開することが求められると導き、専門性を向上する前提には、人間性が重要になることを指摘した。 | |
| 『改訂 はじめて学ぶ社会福祉』(共著) | 令和2年3月 | 建帛社 | 第4章「社会福祉の行財政と実施機関」を担当。厚生労働省、こども家庭庁、福祉事務所や児童相談所などを解説。また、社会福祉財政と費用負担として福祉サービスの利用方法なども解説した。 | |
| 『子ども家庭支援論』(共著) | 令和2年3月 | 北樹出版 | 第12章「要保護児童等及びその家庭に対する支援」を担当。虐待の発生要因や虐待が子どもにおよぼす影響を解説。また、要保護児童の家庭支援として保護者が利用できる社会資源について事例をもとに解説した。 | |
| 『子育て支援』(演習)(共著) | 令和2年3月 | 北樹出版 |
第13章「子ども虐待の予防と対応」を担当。子ども虐待の定義、虐待の発生要因、子ども虐待と関係機関について解説。保育所で想定される虐待を受けた子ども、その保護者への対応について3点の事例演習を設定した。 第14章「要保護児童等の家庭に対する支援」を担当。児童養護施設の支援の流れ、親子関係再構築の注意点などを解説。また、施設で生活を送る子どもや保護者の支援、家庭復帰における他機関との連携など事例演習を3点設定した。 |
|
| 『新・子ども家庭福祉』私たちは子どもに何ができるか(共著) | 令和2年11月 | 教育情報出版 |
第1章-2 「子ども家庭福祉の歩み」を担当。子ども家庭福祉の歩みとして、江戸時代まで、明治、大正、昭和(戦前)時代、(戦後)から平成時代に分類して解説した。 第6章-3 「ひとり親家庭への支援」を担当。「ひとり親家庭の現状と生活課題」「ひとり親家庭への支援」「ひとり親家庭への各自治体の取り組み」を解説した。 |
|
| 実務家教員の実践経験を効果的に活用するには-学生の声からの考察-(単著) | 令和4年3月 | 湘北紀要 第43号 | 児童福祉施設等の実務経験者として、現場で培った実践経験を授業で伝える実践的教育を重要視してきた。本稿では、2年生を対象にアンケートを実施し、授業で伝えてきた実践経験談の評価を得ることにした。その評価をもとに、実践経験の効果的な活用について考察した。 | |
| 保育実習Ⅰ(施設)の代替授業-学校内演習の取り組みについて-(共著) | 令和4年3月 | 湘北紀要 第43号 | 新型コロナウイルス感染症の流行により、2020年度の保育実習Ⅰ(施設)は34施設から中止連絡があった。代替授業として取り組んだ学校内演習を振り返るとともに、今後のあり方について考察した。 | |
| 実務家教員の実践経験が学生に与えた影響について-テキストマイニングを用いた自由記述の分析-(単著) | 令和5年3月 | 湘北紀要 第44号 | 実務家教員の実践経験が学生に与えて影響について、テキストマイニングを用いて分析、考察した。対象教科は社会的養護Ⅰ。分析にはアンケート調査の自由記述を用いた。その結果、授業を通して社会福祉に関心や問題意識を持つ学生が増えるなど、効果があらわれたことが確認できた。 | |
| ヤングケアラーの歴史的考察(単著) | 令和6年3月 | 湘北紀要 第45号 | 本稿では、ヤングケアラーのような子どもたちが存在していたことを明らかにし、彼らが背負っていた背景や問題を歴史的視点で振り返り検証した。その作業の一環として、史実に基づく史料を取り上げた。 | |
|
学会および 社会での活動 |
【所属学会】 日本子ども虐待防止学会、日本仏教社会福祉学会、日本仏教教育学会、佛教大学仏教学会 【社会活動】 厚木市放課後児童クラブ施設の整備及び運営に係る技術提案書特定委員会委員(~2021年3月)、厚木東高校学校運営協議会委員(~2024年3月) |
|||