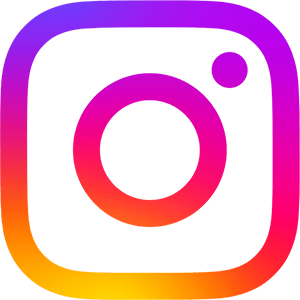教員一覧(2025年度)
生活プロデュース学科
奥脇 菜那子
- 講師
- ファッションコース主任

プロフィール (自己紹介)
テキスタイルや色彩学、ファッションデザインなど、ファッション分野の科目を担当しています。
専門は衣服の素材です。服の素材である繊維や糸、布の性質は、デザインやシルエット、機能性、着心地の良さなど、さまざまな要素に影響を与えます。そのため、素材を知ることは、よりよい衣生活をプロデュースするためのヒントになります。
学生の皆さんと一緒に考え、たくさんお話をしながら、豊かな衣生活を目指して学び続けていきたいと思っています。
主な担当科目
- テキスタイルの基礎
- パーソナルカラー入門
- ファッションデザイン論
ゼミナール研究テーマ
ファッションショーをプロデュース!
11月に開催されるファッションショーを目指して、衣装製作とショーの企画・運営を行います。
ファッションショー終了後は、ファッションや衣生活に関連する卒業研究課題に取り組み、発表します。
学生へのメッセージ
毎日の生活の中で、「なんでだろう?」「不思議だな」「困ったな」「面白いな」と感じたことが、皆さんの学びのヒントになります。
生活やファッションについて感じたことや考えたことを、ぜひ、友人や家族、教員など、周りの人たちとたくさんお話してください。
そして、意見を交わし合う中で、新たな気づきを得ることを大切にしてください。
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
| 保有学位 | 修士(家政学) 日本女子大学 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
研究分野 | 被服学、衣材料学 | ||
| 著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
| 「生活者」の視点から考える 持続可能性とウェルビーイング: 山梨の織物産地が育んだ人・技術・地域の未来(共著) | 2025年1月 | 日本女子大学総合研究所紀要,第27号,研究課題77 | 本研究は、「生活者」の視点から持続可能性とウェルビーイングを考察し、特に山梨の織物産地に焦点を当てたものである。家政学の発展とその社会的役割を振り返り、持続可能な地域産業の再生を「生活者」の視点から分析するとともに、山梨のハタオリ産地の現地調査やテキスタイル風合い計測プロジェクトを通じて、繊維産業の未来と課題を検討した。 担当部分:第6章 山梨ハタオリ産地現地調査と山梨テキスタイル風合い計測プロジェクト |
|
| 乳幼児肌着に関する保護者の意識調査(共著) | 2023年3月 | 日本女子大学紀要家政学部,Vol. 70,p. 147-153 | 乳幼児の肌着購入に関する保護者の意識を調査し、肌トラブルの実態や購入時の重視点を分析した。調査の結果、肌トラブルを経験する乳幼児は多く、特に1歳以上の幼児になると肌トラブルの経験率が高くなることがわかった。主な原因は衣服のタグ、生地との摩擦、縫い目との摩擦であった。 保護者は肌着購入時に素材を最も重視し、特に綿100%を好む傾向があった。肌触りのよさや動きやすさが重要視される一方で、デザインや価格、ブランドには関心が低かった。また、縫い目による皮膚刺激を懸念し、できるだけ刺激を軽減したいと考える保護者が多かった。 |
|
| 日本女子大学卒業生小林孝子の衣服標本研究―1930年代の日本女子大生とその家族の衣生活―(共著) | 2022年11月 | 日本女子大学総合研究所紀要,第25号,研究課題72 |
本研究は、日本女子大学卒業生・小林孝子の衣服標本から1930年代の女子大学生とその家族の衣生活を分析したものである。衣服標本を基に繊維組成や組織、色柄の傾向を調査するとともに、当時の消費主義の影響や戦前の衣生活について考察し、近代日本の服飾文化を理解する上での貴重な資料としての意義を明らかにした。 担当部分:Ⅲ 小林孝子衣服標本の貼付試料の組成と組織について |
|
| ポリウレタン混ストレッチ織物の経年による力学的特性変化(共著) | 2022年3月 | 日本女子大学紀要家政学部、Vol.69、p.113-119 | ポリウレタン混織物はストレッチ性に優れるが、経年劣化や型崩れがデメリットとして挙げられる。本研究では、購入直後と10年以上経過後の同一試料の力学的特性値を比較し、特性変化の傾向を分析した。また、新品試料に加速劣化試験を施し、特性変化に影響を及ぼす要因について検討した。ジャングル試験による劣化処理では生地が伸びやすくなり、経年劣化と同様の変化が確認された。一方、着用疲労を再現した試験では、生地が薄くなり、弾性が低下し伸び率が減少することが確認された。これにより、経年劣化と物理的劣化の違いが明らかになった。 | |
| ECサイトにおける布の風合いに関する表現と消費者の意識(共著) | 2022年3月 | 繊維製品消費科、Vol.62(3)、p.177-184 | ECサイトでの衣服販売では、布の風合いを消費者に伝えることが難しい。本報では、実際のECサイトの調査と大学生への意識調査を通じて、風合いの表現方法と消費者の求める情報を分析した。その結果、風合いは主に「商品画像」と「説明文」により表現され、一部で簡易な指標が用いられていたが、詳細な指標はなかった。消費者は特に「厚さ」「透け感」「ドレープ」「ハリ」などの情報を求めており、今後は客観的な指標を用いた表現が課題となる。 | |
| アパレル企業を対象にしたECサイトにおける布の風合い表現に関する調査(共著) | 2021年3月 | 繊維製品消費科学、Vol.62(11)、p.733-740 | アパレルECサイトの利用増加に伴い、返品も増えており、その一因として「布の風合い」のイメージ違いが挙げられる。風合いは感覚的要素が強く、ECサイト上で伝えにくい。そこで、風合いを客観的に伝える手法について検討するため、アパレル企業へのアンケート調査を実施し課題を分析した。その結果、約8割の回答者が風合いの客観的指標化の必要性を感じていた。特に「布の厚さ」や「柔らかさ」が返品理由や風合い表現で重要視されており、消費者に伝えるための客観的な表現方法が求められていることが明らかになった。 | |
| 各種清拭素材の肌への刺激評価―摩擦特性からの検討―(共著) | 2019年3月 | 日本女子大学紀要家政学部、Vol.66、p.145-149 | 乳幼児の口周りの汚れを拭き取ることによる肌トラブルを軽減することを目的として、タオルやガーゼなどの清拭用布による肌への刺激を、乾燥状態と湿潤状態における摩擦特性から検討した。試料の平均摩擦係数(MIU)を測定した結果、湿潤状態ではMIUが増加する傾向があるが、負荷荷重が増加するとMIUは減少することがわかった。さらに、摩擦力の増加率を算出したところ、大半の試料において、乾燥状態よりも湿潤状態で増加率が低下しており、拭く力を強くした場合には清拭素材を湿潤させることで肌への負担を軽減できることが示された。 | |
| ミシン縫製におけるニットの地糸切れ防止に関する研究―繊維素材と水分付与効果の関係―(共著) | 2012年9月 | 繊維製品消費科学、Vol.53(9)、p.723-730 | 本研究では、ニット生地の縫製時における地糸切れ防止策としての水分付与効果と繊維素材の関係を検討した。綿とモダルのニットを用いた縫製実験の結果、綿ニットでは水分付与により地糸切れが減少したが、モダルニットでは逆に増加する傾向が見られた。混用ニットは綿と同様の低減効果を示した。この傾向の違いは、モダル編糸が水分により膨潤することによる編糸の自由度の低下と、エッジ強さの減少が複合的に作用したものと考えられる。本研究から、水分付与の効果は素材に応じて慎重に判断すべきことが示唆された。 | |
|
学会および 社会での活動 |
日本家政学会(若手の会 副代表)、繊維学会、日本繊維製品消費科学会 | |||