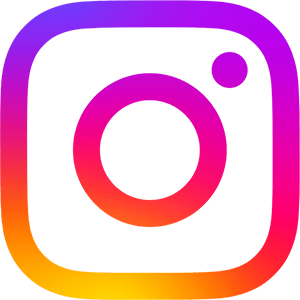教員一覧(2025年度)
総合ビジネス・情報学科
岩村 夏樹
- 講師

プロフィール (自己紹介)
大学卒業後、インターネット専業の証券会社で3年間、システムや財務を担当しました。尊敬する社長のもとで、黎明期のネットを使った新しい形の金融業を体験したことは忘れられません。その後は神奈川県の商業科教諭として19年間勤めました。まだ誰も知らないことに手を伸ばすことが大好きです。合唱も大好きです。皆さんが学生生活とこれからの人生を”謳歌”できるように応援します。
主な担当科目
- ビジネス社会の基礎Ⅰ
- ビジネス社会の基礎Ⅱ
- 現代ビジネス事情
ゼミナール研究テーマ
経営戦略・アントレプレナーシップ
国内企業の経営者の著書をゆっくり読みながら、経営戦略や経営哲学について理解を深め、新しいことを考案し、企画し、実行するアントレプレナーシップを育んでいきたいと考えています。ゼミでは内容をまとめ、議論するだけでなく、本や情報との向き合い方、人生のライフステージにおける学び方までを一緒に考えていきます。経営戦略という言葉は、なんとなく堅苦しい印象を持つ言葉かもしれませんが、物事を俯瞰して眺め、ちょっと立ち止まって考えていく癖をつけていけば、その後の人生をよりよくする術が見つかっていくものです。良い戦略を考えることは良い人生を考えること。そして、戦略の裏には哲学があり、哲学を醸成するに至った過程の起爆剤としてアントレプレナーシップが存在すると私は考えています。新しいこと、興味深いことを一緒に学ぶ仲間との時間を大事にしたいと思っています。
学生へのメッセージ
学ぶこと、新しいことを知ることや理解することは、それ自体が本当はとても楽しいものです。でも忙しい学生時代はなかなかそのことに気が付けません。湘北での2年間で、これは面白いな、と思うものを一つでも探してください。ビジネスでなくてもかまいません。もし希望する進路を見つけたら、実現の手助けをさせてほしいと思います。
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
| 保有学位 | 学士 一橋大学商学部、経営学修士(MBA) 一橋大学大学院商学研究科 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
研究分野 | 経営戦略 アントレプレナーシップ ビジネス教育 | ||
| 著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
|
アントレプレナーシップ ~実践の手引き~(共著) |
2021年3月 | 神奈川県立麻生総合高等学校 | アントレプレナーシップを高等学校で行う際の手引きとして授業方法、カリキュラムや評価方法をまとめた、全国でも珍しい小冊子である。麻生総合高校では、アントレプレナーシップの授業を通して、生徒が現代社会への関心を高め、ものの見方や考え方を広げることを目指している。授業では、課題発見・分析力、プレゼンテーション力、課題をやり遂げる力の3つの資質・能力を育成することを目指す。授業では、PBL(Project Based Learning)を取り入れ、外部講師や企業との連携を重視している。生徒は、上記の授業を通じ、企業から提示された課題に対してチームで解決策を検討し、プレゼンテーションを行う過程を繰り返すなどの他校で使用可能な具体的指導方法が示されている。 | |
| 高等学校用教科書 ビジネス経済(共著) | 2014年4月 | 実教出版 | 商業高校のビジネス経済の授業にて使用する教科書である。 | |
| 高等学校用教科書 ビジネス基礎(共著) | 2013年4月 | 実教出版 | 商業高校のビジネス基礎の授業にて使用する教科書である。 | |
| アベノミクスで学ぶ日本経済 | 2013年 | 金融広報中央委員会 |
金融教育教材としてアベノミクスを導入した珍しい授業の実践報告である。アベノミクスの基本を「お金の流れ」として捉え、金融緩和、財政政策、成長戦略の三本の矢を、経済再生のための考え方の一つとして中立の立場から授業に取り入れた。授業では、生徒の頭の動きを想定した発問や板書計画、観点別評価を取り入れ、生徒の興味関心を引き出し、理解を深める工夫を行った点も示されている。また、県立学校公開講座として地域住民や他校の生徒も対象にアベノミクスを解説し、好評を得た点も挙げられている。生徒からは、政策への賛否両論ありつつも、経済への関心を高めるきっかけになったという意見が寄せられた点が報告されている。 <第10回金融教育に関する小論文・実践報告コンクール(2013年)【実践報告部門】優秀賞 受賞論文> |
|
| 信用取引で教える証券決済の正体─株式基礎を学び終えた高校生たちへ─ | 2011年 | 金融広報中央委員会 |
金融教育においてタブー視されがちな「信用取引」を教材として取り上げ、生徒の金融知識や問題解決能力の向上を目指した点を報告している。信用取引の存在意義から担保、貸株の理論までを教えることで、生徒は証券決済のリアルな姿を理解し、金融に対する興味を深めた。この授業を通じて、リスク教育の重要性や、金融の仕組みを深く理解することの必要性を生徒に伝えることができた点が報告されている。 <第8回金融教育に関する小論文・実践報告コンクール(2011年)【小論文部門】奨励賞 受賞論文> |
|
| マーケットからの招待状 (商業教育資料78号(じっきょう)) |
2008年3月 | 実教出版 | 著者が神奈川県立厚木商業高校在任中、金融経済教育の必要性に応え、3年生選択科目「課題研究」にて株式市場に焦点を当てて指導した「初めての株式」についての報告と提言である。生徒が興味を持てるようニュースや事例を取り上げ、最新の法令に則った情報を提供。クイズ形式での知識確認や、企業のニュースを用いたケーススタディ、株式ゲームを通じて、生徒の学習意欲を高め、金融経済への関心を深めた。また、教員間のネットワーク構築や企業・各種協会のサポート、証券外務員の資格取得も視野に入れ、金融経済教育の普及と発展を目指すといった内容がまとめられている。 | |
| 株式学習ゲームによる学習効果の測定と評価 ~授業における観点別評価への一試案~ | 2007年 | 日本証券業協会・東京証券取引所グループ | 著者が神奈川県立厚木商業高校の3年生向け授業で、金融教育への興味喚起と学習効果の測定・評価に取り組んだ点を報告している。株式学習ゲームを使用し、生徒の【1】金融知識の理解、【2】思考力、【3】根拠に基づいた判断力の育成を目指した。評価は観点別評価(意欲、思考、技能、知識)を導入し、授業中の発言やグループワークの議事録、提出プリントなどを多角的に評価した。想定外の効果として、M&Aの予想を立てるグループが現れたり、グループワークの意思決定が迅速化される成果が挙げられている。評価基準の明確化、学校全体での取り組みと外部連携の必要性を今後の課題として挙げている。 <平成19年度 株式学習ゲームに関する小論文コンテスト 【教諭の小論文】最優秀賞 受賞論文> |
|
|
学会および 社会での活動 |
2012年12月 金融経済教育フォーラム 担当講師 兼 パネリスト 東京証券取引所 | |||