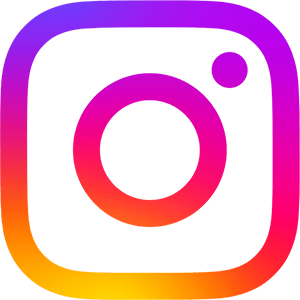教員一覧(2025年度)
生活プロデュース学科
二見 総一郎
- 講師
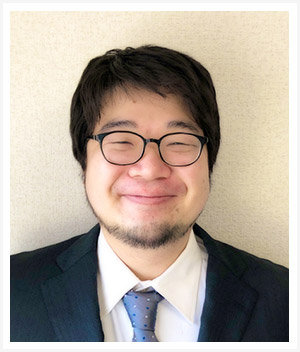
プロフィール (自己紹介)
主に、子どもについて学ぶ科目を担当しています。「生きづらさ」を抱えた子どもたちにとって、安心できる居場所がある社会はどうやったらつくれるのだろうか、という問題に関心を持って学び続けています。その過程で大阪にある小学校に1年間通い、子どもたちと共に学び合う中で、どんな背景を持つ子どもも一緒に対等な関係で学ぶ「インクルーシブ教育」に強く関心を持つようになりました。
映画を観ることと、美味しいものを食べることが好きです。
主な担当科目
- 子供と福祉
- 家族援助論
- 生活とSDGs
ゼミナール研究テーマ
子どもと社会について考える
現代社会において、子どもたちは様々な「生きづらさ」を抱えながら生きています。そんな子どもたちを取りまく社会的な問題について、文献(本、論文、絵本、小説、漫画など)や映像資料(映画、ドキュメンタリー、ニュースなど)を通じて学び、自分たちがこれまで生きてきた体験と照らし合わせながら子どもに関する知見を深めます。そこで得られた学びをもとに関心のあるテーマを選び、卒業研究に取り組みます。
学生へのメッセージ
大学での生活は高校までの生活から大きく変化します。出会う人たちも違えば、授業の形式も内容も違う。これまで読んだことのなかった本と出会い、これまで行ったことのない場所に行き、見たこともない風景を目にすることもあります。だからこそ、自分と違った考え方や価値観とたくさん出会うことになり、悩むことも多ければ、その分学ぶことも多いでしょう。そうやって学んでいくことが、これからのみなさんの人生を、みなさんがつくっていく社会を豊かなものにしてくれます。みなさんと一緒に学べることを、心から楽しみにしています。
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
| 保有学位 | 修士(教育学) 東京大学大学院教育学研究科基礎教育学コース | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
研究分野 | 教育史、インクルーシブ教育 | ||
| 著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
| 「教員の地位に関する勧告の受容過程」(単著) | 2020年3月 | 『東京大学大学院教育学研究科紀要』第59巻、pp. 295–305 | 1966年にILO・ユネスコで採択された「教員の地位に関する勧告」の日本における受容過程を検討した。「教員の地位に関する勧告」が、日本の教師の専門性に関する議論を大いに活性化させたことを指摘した。 勧告の草案作成段階における国際会議において、教師の専門性の重要な要素として、教科の専門的な知識を持つことのみならず、教育課程を総合的に把握し、編成することにあると強調されていることを明らかにした。本論文を通して、日本の教師教育が、この勧告の内容に多大な影響を受けながら発展してきたと位置づけた。 |
|
| 『障害児の共生教育運動――養護学校義務化反対をめぐる教育思想』(共著) | 2019年11月 | 東京大学出版会 | 本書は、1979年の養護学校義務化の実施に反対し、障害児を地域の普通学校へと進学させようとした運動について、具体的事例を個別に分析することを通して、「共生」の教育思想とその実践が提起した問題を歴史的に検討したものである。 担当個所において、関東を中心にその反対運動が展開される中で、大阪府枚方市の運動の中心にいた、宮崎隆太郎という一人の教師を検討した。障害児と健常児が共に学ぶ実践の実現を目指しながらも、障害児の教育を充実させるために「(障害児を)ホンネのところで拒否する思想」をはらむ現状の学校や教師の在り方を追認せざるをえないジレンマに陥った宮崎の挑戦を分析することを通して、学級や学年の垣根を越えて学校教育課程全体を再構築することの必要性を指摘した。 担当部分:第10章「共生教育運動における教師のジレンマ――大阪枚方市・宮崎隆太郎の挑戦」(pp. 197–216) |
|
| 『新版 教育課程論のフロンティア』(分担執筆) | 2018年9月 | 晃洋書房 | 本書は、教育課程論について、思想、法令、歴史、政策動向、実践、評価、経営、外国との比較など、多角的な観点からアプローチしたテキストである。 担当個所において、インクルーシブ教育の概要を解説した。文部科学省が、2012年に「共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」報告の中で、インクルーシブ教育の重要性を打ち出したことを紹介した。続いて、インクルーシブ教育の実践校として知られる大阪市立大空小学校の事例を取り上げた。同校では、「全校道徳」や「ふれあい科」といった独自のカリキュラムを作成・実践しており、障害の有無にかかわらず子どもたちが互いに学び合う、インクルーシブを目指す教育課程編成の先駆的な事例となっていることを指摘した。 担当部分:第4章「コラム3 インクルーシブ教育」(pp. 53–55) |
|
| 「みんながつくる大空小学校 第2ステージ たった一つの約束・やり直し」(単著) | 2018年4月 | 『月刊 教職研修』2018年5月号、p. 58 |
大阪市立大空小学校には、校則がない代わりに「自分がされていやなことをしない、言わない」という「たった一つの約束」があり、これを破ったときには子どもも大人も「やり直し」をしなければならないことを紹介した。 この「やり直し」は約束を破った罰則では決してなく、相手の嫌なことや自分の気持ちを知ることで、お互いの弱さや違いからお互いをより深く知り、子どもの心の成長を促すための、学びのシステムであったと位置づけた。 |
|
| 「インクルーシブ教育における実践的思想とその技法:大阪市立大空小学校の教育実践を手がかりとして」(共著) | 2016年3月 | 『東京大学大学院教育学研究科紀要』第55巻、pp. 1–27 | 本論文は、大阪市立大空小学校の思想と実践を分析することを通して、インクルーシブ教育を可能にするための教師たちの実践的思想と技法を検討するものである。 担当個所においては、大阪市立大空小学校における、子どもたちがお互いを思いやりながらともに学び合う道徳心の育成のための、独自のカリキュラムについて論じた。例として、他者と生きることを学ぶ「ふれあい科」は教科を横断した内容を含んでおり、全校生徒が一つのテーマについて共に学び合う「全校道徳」は単元・学期・学校を越えた長期的な視野に基づいて編成されていることなどを取り上げた。 またそれは決して一人の教師の努力のみで可能になっていることではなく、学校全体で多角的に子どもの学びを見ようとする理念に基づいて行われていることを明らかにした。 担当部分:第4節「「すべての子どもに開かれた学びの場」をつくるための技法」(pp. 19–25) |
|
|
学会および 社会での活動 |
日本教育学会、大阪市立大空小学校にて学校運営協議会委員(2016.4-2019.3) | |||