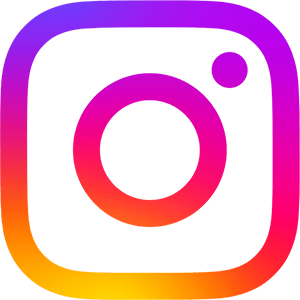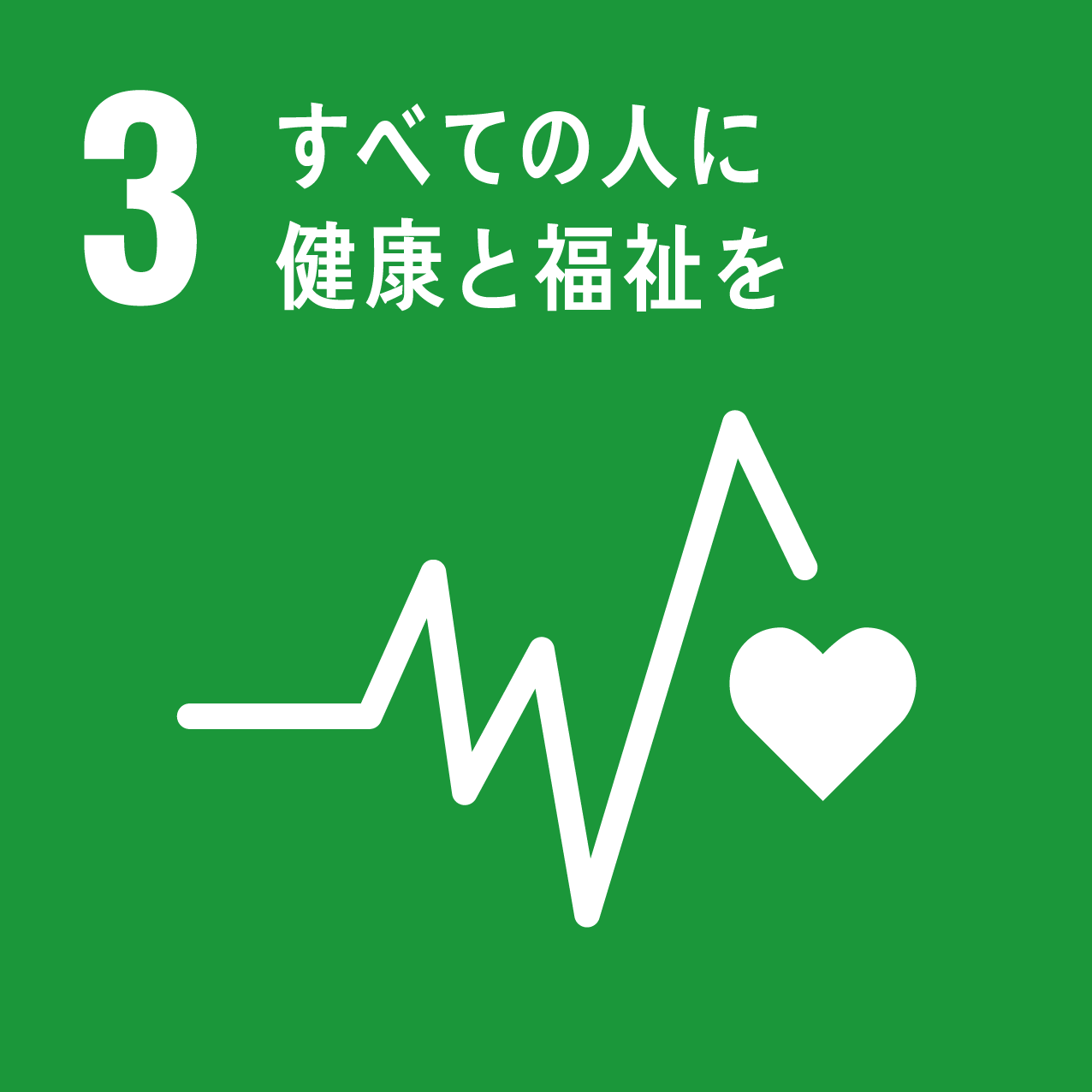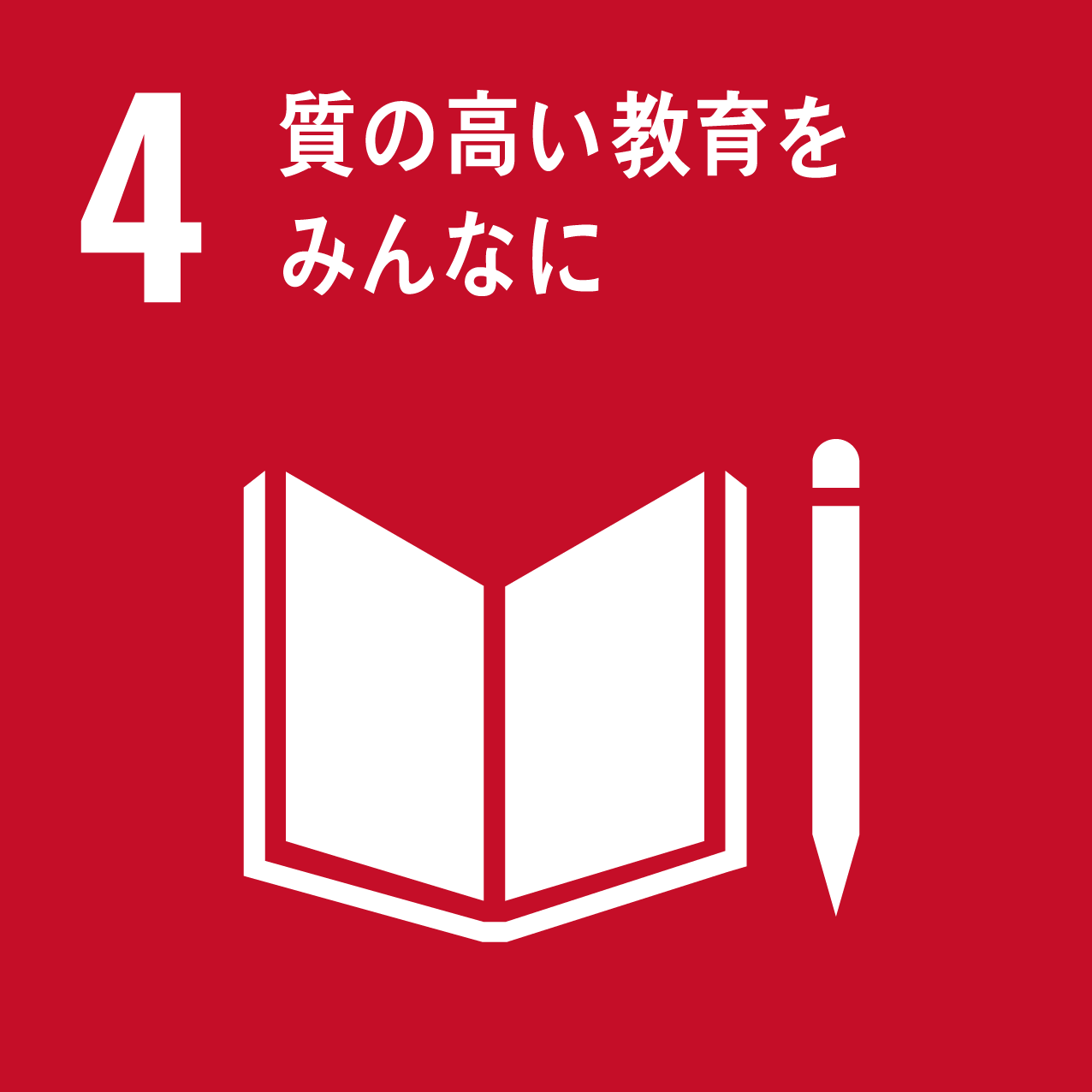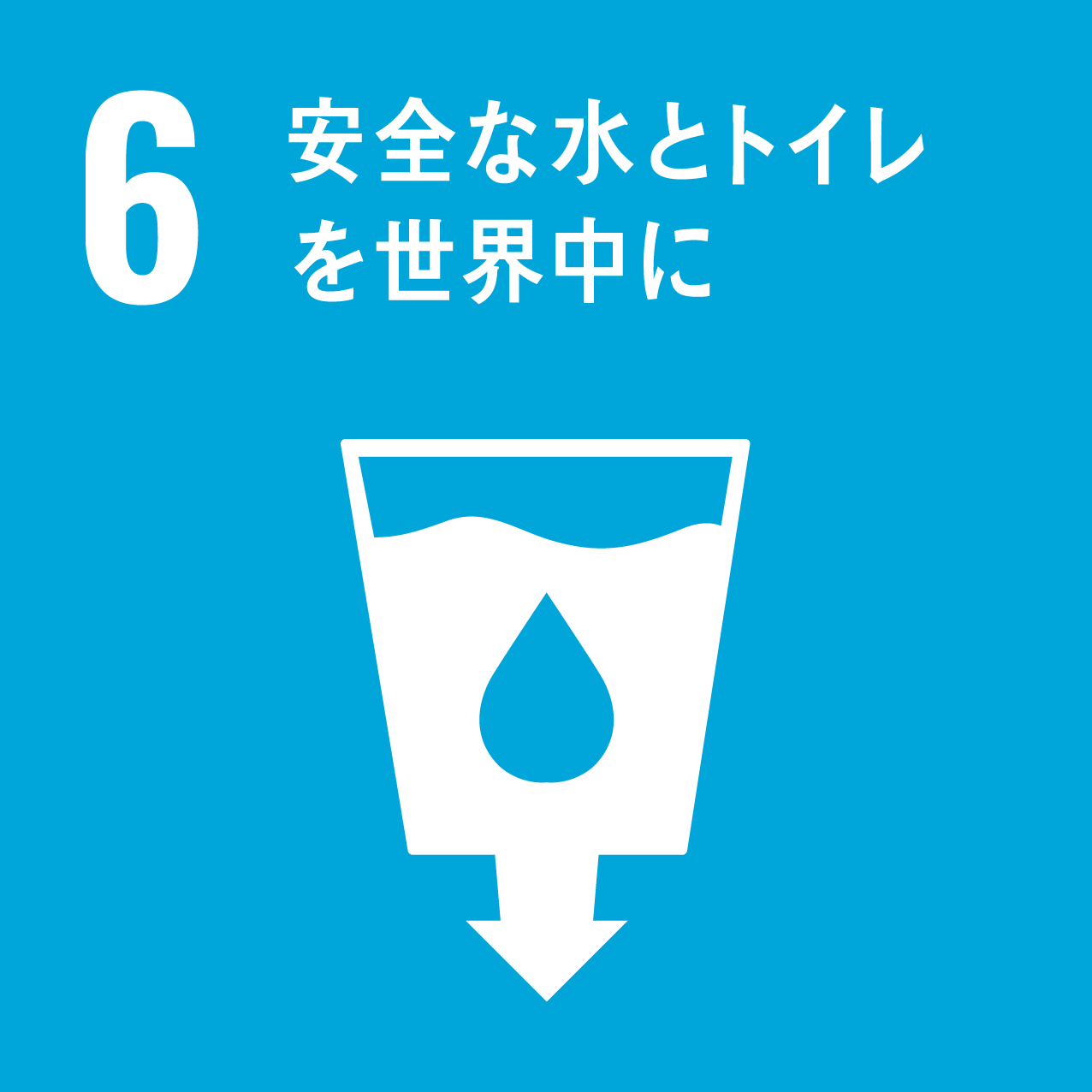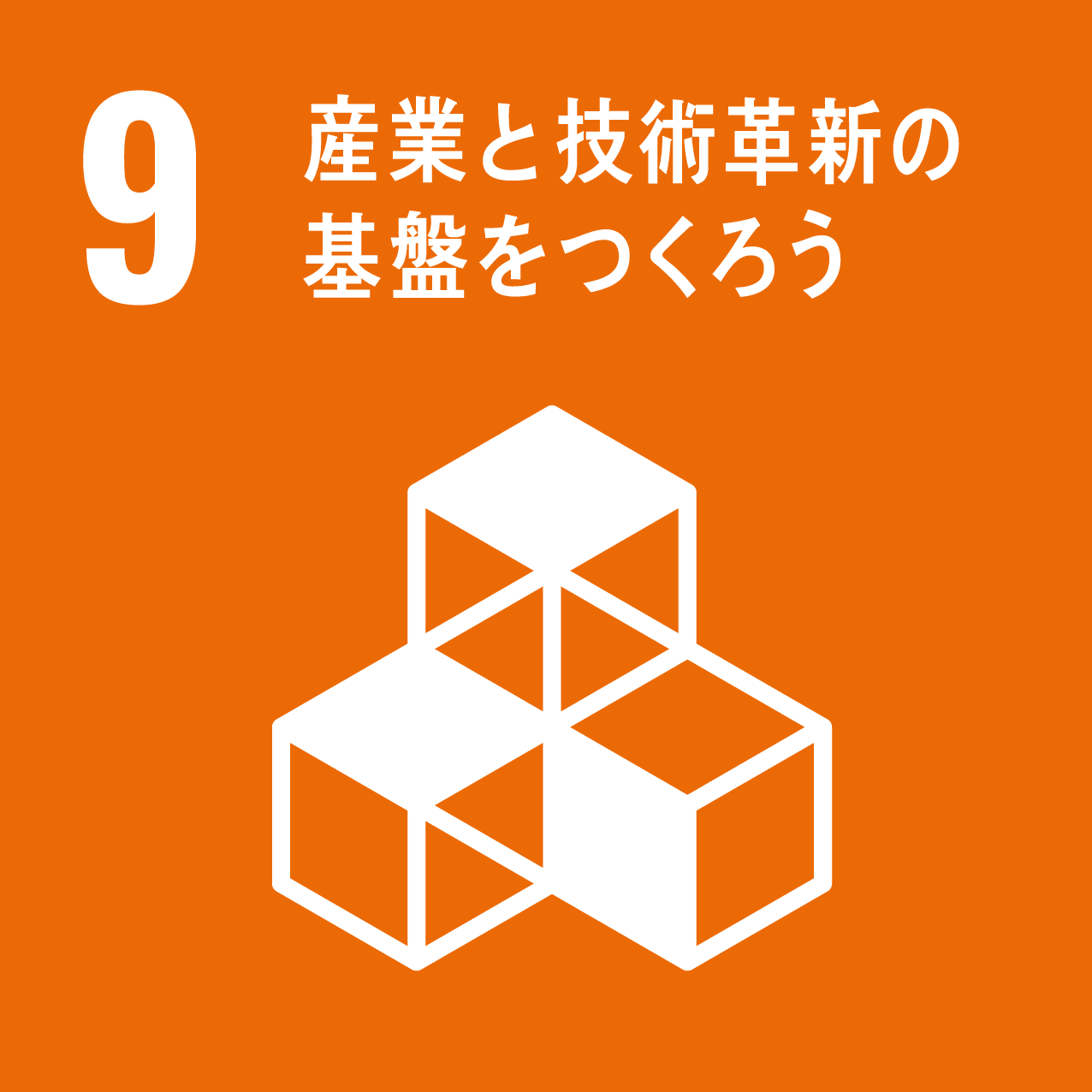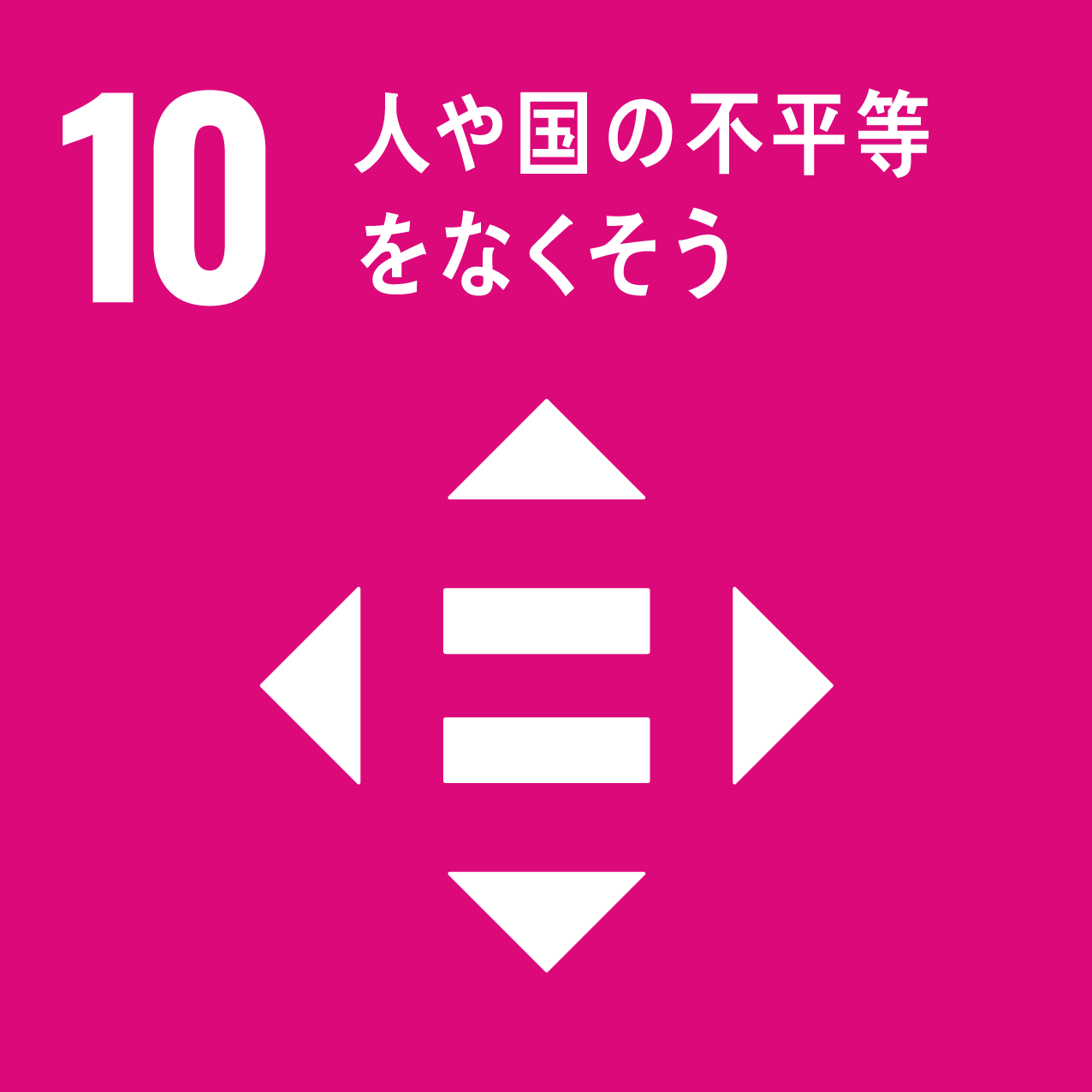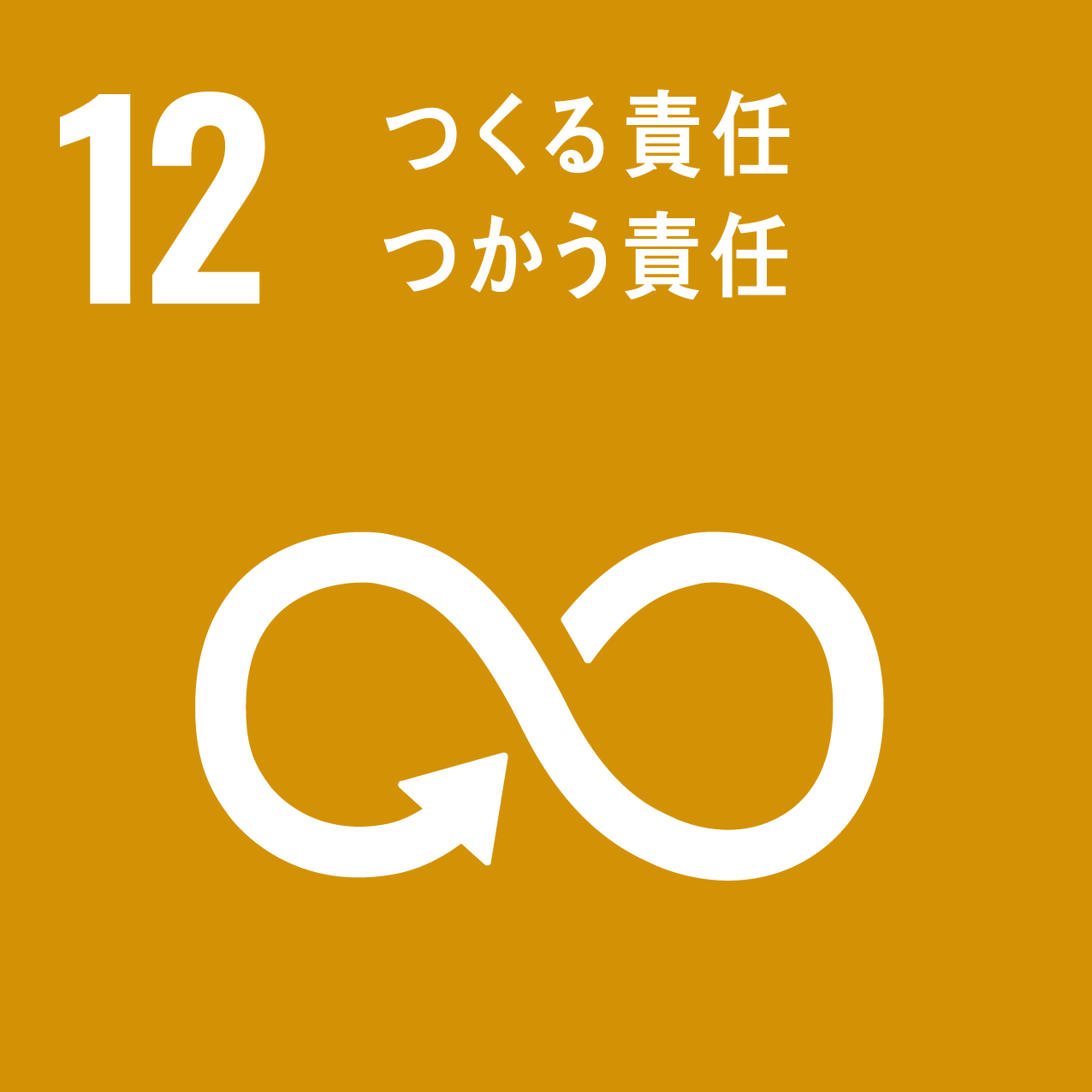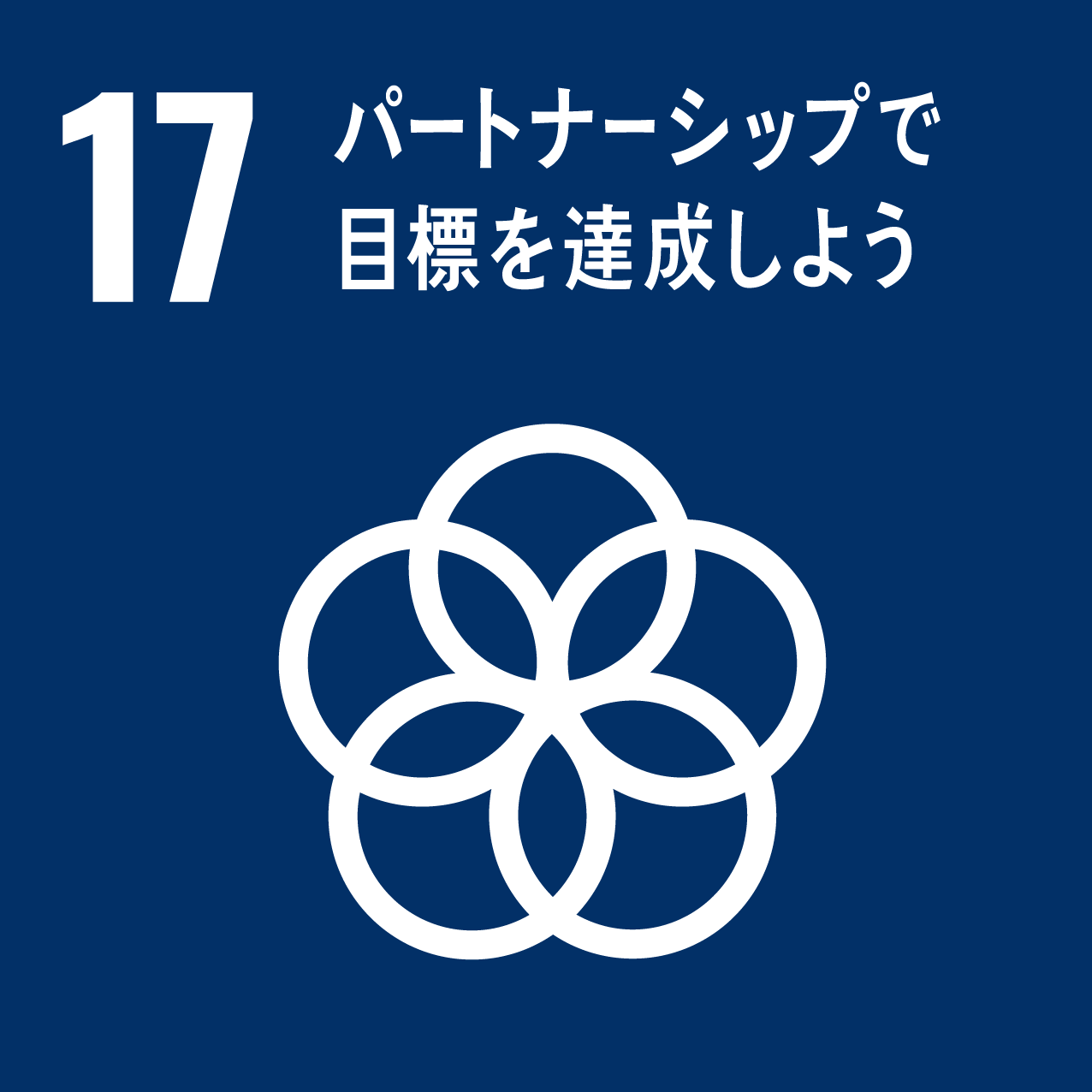湘北SDGs
【授業紹介】「生活とSDGs」豊永翔平氏による特別授業を実施(2025年7月、2回)
生活プロデュース学科では、「生活とSDGs」の授業に、外部講師豊永翔平さんをお招きし、「気候変動時代における新たな食と農のかたち」をテーマにお話し頂きました。豊永さんのオンラインと対面によるそれぞれの特別授業に、学生は真剣に耳を傾けていました。
〔考古学から農業の世界へ〕
豊永さんは、大学で考古学の研究される中で、文明が衰退した要因の一つが、気候変動による食料難であったことに気づかれたそうです。今、80億人が暮らす地球では、温暖化、淡水の枯渇、耕作地の減少などにより、近い将来、深刻な食料不足が起きると予想されています。豊永さんは「21世紀は食料と水の戦争の時代」とお話し、私たち一人ひとりが未来の地球を真剣に考えていく時代にきていることを改めて感じました。豊永さんは、気候変動と食料不足の問題を解決するために、26歳で起業、沖縄に研究開発拠点Cultiveraを設立し、環境に優しい独自の栽培技術「Moisculture」を開発しました。これは、特殊な繊維層に水をしみこませ、気化した湿度で野菜を育てるという画期的な特許技術です。
〔POMANATOMATO〕
今回、豊永さんには、「Moisculture」の技術で栽培されたトマト「POMONATOMATO」を受講生にご提供いただきました。豊永さんによると、「POMONATOMATO」は、「トマトを最小限の水分で育てることで、生きようとする力が強くなり、野菜本来の生命力を引き出すことができる」とのことです。水耕栽培と比較して水使用量を90%減少でき、また、糖度や酸度もコントロールすることができるとのことです。また、2023年に、トマトとしては世界で初めてGABAの機能性表示食品の届出が受理されたことが、大きく報じられました。
豊永さんがCEOを務める株式会社ポモナファームは三重県多気町にあり、北緯34度32分線に位置します。豊永さんによると「この線は世界の四代文明や日本の稲作地帯を照らした豊穣の道」とのことです。「POMONATOMATO」の奥深い味わいは、人類が語り継いできた文明の記憶でもあるのか。豊永さんのお話と「POMONATOMATO」には、そのようなロマンをも感じました。
〔海上都市構想〕
現代は、人間の経済活動の影響により、地球上の各地において気候変動に起因する異常現象が発生しています。例えば、①毎年複数の大型台風の被害が発生、②世界的な干ばつ、③感染症の発生、④超集中豪雨、⑤水不足、⑥世界的山火事、⑦海面上昇、⑧熱波、⑨農業壊滅、➉死にゆく海、⑪大気汚染、⑫気候難民などです。この先、人々が安心して住み続けてゆくことが出来るエリアが減少し続けるとすれば、これまでに誰も試みようとしなかった新たな取り組みが必要となります。豊永さんは、株式会社N-ARKが推進する、海上都市構想のプロジェクトにも関わられています。海洋都市構想とは、民間海洋ビジネスイノベーションにより、海洋を新たな経済圏=NEW OCEANとし、気候変動に対してレジリアンスな海洋経済圏を作り出していくものです。「気候変動の時代だからこそ、新しいことにチャレンジすることが大切」という言葉で、豊永さんは講義を締めくくられていました。
〔学生たちの感想〕
豊永さんの講義を聞いた学生たちの感想には、
「今日の講義を受けて、日本の農業状況に関して細かく知ることが出来ました。高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加、そして食料自給率の低さといった課題がたくさんあることを学び、今の日本の農業の課題に関して考えるきっかけになりました。」
「ファッションコースで服の事を学んでいますが、服の原料となるコットンも取れる回数が減るということを聞きました。今はお金があれば簡単に服が手に入りますが、今のように簡単に作れる機会が減ってしまってりして価値も高くなる可能性もあるのかもしれないように思います。」
といった、今の社会の問題を理解することができたという声が多くみられました。
また、
「たくさんの時間をかけて問題を解決してきてもほかの問題が増えていて、わたし自身できることは少ないけどなにか一つでも行動することが大事なんだなと感じました。」
「野菜の育て方が進化していたり、地球温暖化に対応する技術ができたりしていると聞いて進化しているのはAIだけではないんだということを学ぶことが出来ました。これからの未来に向けて私にもできることはないか考えながら生活していこうと思います。」
といった、今後の自分の日々の生き方を見直す意見もあり、学生たちが深く学んだ様子が見られました。
(生活プロデュース学科 近藤哲、二見総一郎)