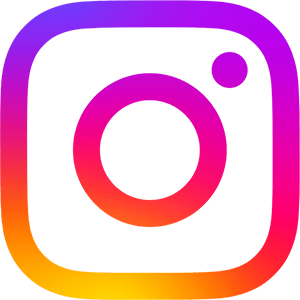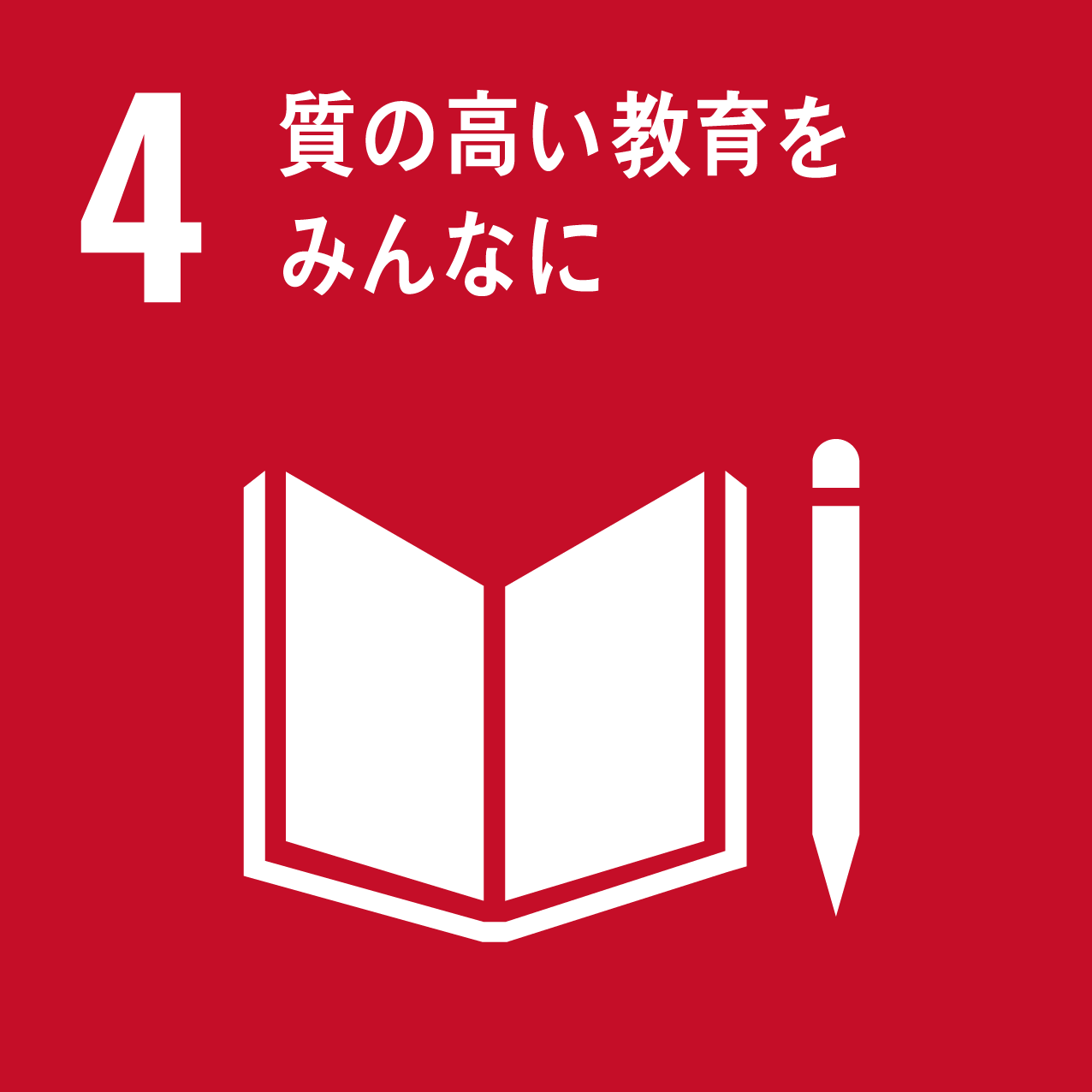湘北SDGs
【授業紹介】「ゼミナールII」生活プロデュース学科2021年度2年生 卒業研究から(2)
テーマ:海外と日本の保育制度
執筆者:チーム 子ども
1.目的
SDGs4番「質の高い教育をみんなに」を実現させるためには、世界の保育制度の現状を知る必要があった為、このテーマを設定した。また、日本では待機児童問題などが存在するが、海外ではどのような課題があるのか比較するため。
2.方法
インターネットによる情報収集、文献調査
3.結果・考察
4カ国の保育制度を比較して、それぞれの国にそれぞれの社会的背景に沿った保育サービスがあることがわかった。
【日本】延長保育や家庭的保育などの多様な保育サービスが存在する為充実しているが、実は大きな問題が存在していることが分かった。それは、待機児童問題だ。待機児童数は1.2万人に減少しているものの、隠れ待機児童の存在や保育士の人材確保など問題解消に向けて取り組む課題は多い。
【スウェーデン】世界の中で最も保育制度が充実している国である。日本では、待機児童数が多いなどの問題があるが、スウェーデンではその問題がほぼない。例えば、待機児童がほぼゼロだということ、子育て中の親の長時間勤務を減らす働きが進んでいることだ。
【アメリカ】収入に応じて保育料が変わるシステムがない等、保育に関する出費が高い傾向にあることが課題である。一方で、生後6週間の赤ちゃんでも預けられるなど両親のより早い社会復帰が実現できる様な仕組みも存在していた。
【中国】保育園の発展に国のサポートが不十分なことが最も大きな課題である。政府は0〜3歳までの保育園にかける資金を増やし、より具体的な政策が必要になる。一方で、女性の社会活躍を後押しする考えから保育園、幼稚園ともに1日保育を行うなど魅力的な点も存在していた。
多くの国や地域では、この就学前教育の制度について社会の変化に追いついておらず深刻な課題になっている。保育所や幼稚園に入所・入園できない待機児童の増加や、子供の引き取りの為に早期退社しなければいけないワーキングマザーやシングルマザーなどの増加がその一例だ。この問題を解決する為、労働条件や基準の見直し、職場やその周辺の保育所や幼稚園の施設、柔軟な勤務時間の採用などが行われている。
(簗瀨)