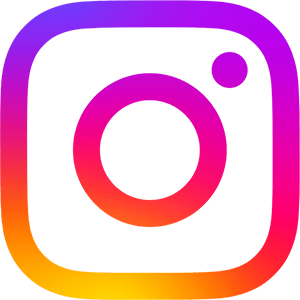質の高い大学教育推進プログラム
平成20年度 文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」に、本学の取組みが選定されました。
「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」とは
文部科学省がこれまで実施してきた「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」と「現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)」を発展的に統合し平成20年度に新設したものです。
大学設置基準の改正などへの積極的な対応を前提に、各大学・短期大学・高等専門学校における、教育の質の向上につながる取組みの中から特に優れたものを選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点的な財政支援を行うことにより、我が国全体としての高等教育の質の保証、国際競争の強化に資することを目的に創設された、文部科学省の事業です。
初回である平成20年度は、全国の国公私立の大学・短期大学・高等専門学校から939件(短大91件)の申請があり、148件(短大17件)が選定されました
プログラム名称:「図書館を実践の場とする学科横断PBL教育」
本学は、これまでも「社会に出て役に立つ人材の育成」をめざして、"PBL"教育手法を活用したICT教育を実践してきました。
※PBL: Project-Based Learning(問題発見解決型教育)
※ICT: Information and Communication Technology
本学の取組は、①情報メディア学科(情報系)を核にして、総合ビジネス学科・生活プロデュース学科・保育学科(非情報系)の学生とコラボレーションで実施すること、②図書館を従来の「静謐な知の集積拠点」から「知的コミュニケーション空間」へと改革してPBL教育の舞台とすること、以上の2つを柱としています。
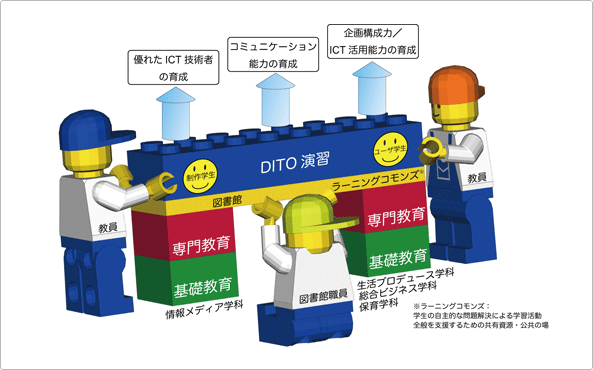
①情報系学生と非情報系学生のコラボレーション DITO演習の3つの例 ※DITO:Do IT Ourselves
情報系の学生と非情報系学生が協力して「自分たちでコンテンツを作りあげよう」という意味のDITO演習。
情報系学生には、現実のニーズに応えるコンテンツ制作を通じて、より実践的な知識や技法を学ぶことができます。また、非情報系学生との共同演習により、ユーザー側の視点の学習、さらにコミュニケーション能力の向上も期待されます。
一方非情報系学生にとっては、制作側(情報系)の学生との共同演習を通して、コンテンツ制作技術を体験的に学ぶとともに、企画構想力やコミュニケーション能力の養成、ICT技術の理解の深化が期待されます。

①ファッションショーの
デジタル演出
②Podcasting資格対策
学習教材作成
③デジタル紙芝居作成と
保育園公演
②ラーニング・コモンズを目指した図書館の有効活用
DITO演習を実践する場として、図書館が生まれ変わります。学生たちが話し合いながら、図書館内の様々な情報や資料を活用してコンテンツを制作するオープンスペースを新設。このように大学図書館の役割を「知的コミュニケーション空間」として活性化して行く取組は「ラーニング・コモンズ」と呼ばれ、世界的な新しい潮流となっています。

採択理由
本取組は、建学の理念であり教育目標でもある「社会に出て本当に役立つ人材の育成」という基本目的のもと、学生の実践力の絶えざる向上をめざすプログラムとして、高く評価できる。 特に、情報系、非情報系を問わず、専攻の異なる全学科の学生が連携しつつ学ぶことのできるシステムの開発は、時代の変化に的確に対応するものとして大きな意義を有する。
また、その開発の過程において、従来の図書館とその職員の機能、役割を見直し、新たな活用をめざしていることも先進的であり、他大学の参考にも大いになり得ると考えられる。取組推進の役割分担や体制も、明確に定められ機能しているように見受けられる。