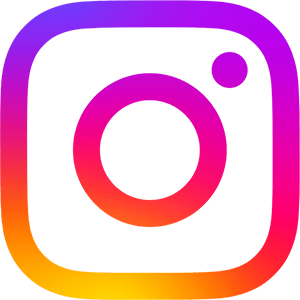教員一覧(2025年度)
生活プロデュース学科
吉川 光子
- 教授
- 副学科長
フードコース主任

プロフィール (自己紹介)
専門は「調理学、調理理論、食生活文化」の分野で、「食生活と健康」や「クッキングⅠ・Ⅱ」他、食に関わる科目を教えています。経歴としては、家電メーカ―で調理器具のソフト開発の仕事を経験し、その後、食に関する研究生活を経て、湘北短期大学に長く勤務しています。
私たちの日常の中にある「調理」というプロセスは、食物を魅力あるものにするのはもちろんですが、ヒトの心身の充足感や精神的な自立とも関わっている、そんなことを伝えられたら幸いです。
主な担当科目
- クッキングⅠ・Ⅱ
- 食生活と健康
- 食品と調理
- 食の情報発信
ゼミナール研究テーマ
調理を通して食物を学ぶ
調理実習を通して、食材についての知識や基本的な調理操作を学び、実習のまとめレポートを作成します。湘北祭をはじめとしたイベントでは、準備、実行、振り返りを通して企画、実践力をつけます。また、食生活に関わる研究課題に取り組み、2024年は災害用備蓄食品をテーマに行いました。
学生へのメッセージ
学生という身分はとてもありがたいものです(誰しも後になってわかることなのですが・・・)。 2年間を充実させ、みんなにとって居心地のいいキャンパスを作る一員となってください。
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
| 保有学位 | 修士(家政学) お茶の水女子大学 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
研究分野 | 調理学、食生活学 | ||
| 著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
| キュウリ呈味成分の分布と貯蔵変化および味との関係(共著) | 2002年 | 日本調理科学会誌,35巻、3号、234-241 | 鮮度低下にともなうキュウリの呈味成分(糖、有機酸、遊離アミノ酸)の変化を測定するとともに「味」の官能検査をおこない、成分の変化との関連を調べた。また、きゅうりの部位による呈味成分の分布とその変化についても調べた。 | |
| 新版 総合調理科学辞典 | 2006年 | 光生館 |
調理科学に関する総合辞典 著者 日本調理科学会員 担当部分:各論「煮る」「煮物」他 |
|
| 本学学生の食生活意識と「食事バランスガイド」の教材としての検討 ―認知度、使用感に関するアンケート調査をもとに― (単著) | 2009年 | 湘北紀要 第30号、119-129 | 授業において「食生活指針」、「食事バランスガイド」を取り上げるにあたり、学生がどの程度認知し、どのような意識をもっているかアンケート調査を行った。また「食事バランスガイド」を利用して2日間の食事診断をさせ、使用感について調査を行った。 | |
| 新版 調理学(共著) | 2020年 | 理工図書 |
「調理科学」テキスト(吉田恵子、綾部園子 編著) 担当部分:ビタミン・無機質の種類と調理、野菜類・果物類の調理性 |
|
| 「地粉」とその製品についての研究(共著) | 2020年8月 | 公益社団法人 飯島藤十郎記念科学振興財団 2019年度年報 第35巻 490-497 | 「地粉」とその製品の現状について群馬、長野、香川、広島、神奈川の5県を対象として調べた。消費者へのアンケート調査を行い、合わせて地域の公的機関や製造、販売に関わる事業者への調査を行った。5県の地粉の成分分析により特性の比較を試みた。 | |
| 調理教育のための短期大学生の技能と経験の調査および技能レベルの分析(単著) | 2021年3月31日 | 湘北紀要 第42号 115-124 湘北短期大学 | 短期大学生の調理技能には差が見られることから2008~2020年の実習初回にアンケートによる調査を行い,個人の能力の把握に利用してきた。計600以上の回答を得たことから全体の分析を行い,授業に生かせる知見を得た。 | |
| 実践力を養う「食の企画と演出」での挑戦(共著) | 2024年3月31日 | 湘北紀要 第45号13-22湘北短期大学 | 授業「食の企画と演出」では、本学の広報部が依頼者となり、学生が「オープンキャンパスの参加者に提供する菓子を考案する」課題に取り組んだ。実践体験型の PBLに挑戦できたことで、学生達には意欲的な姿勢が見られ、課題解決力、実践力など汎用性のある力をつける学びとなった。 | |
|
学会および 社会での活動 |
日本調理科学会、日本家政学会、和食文化国民会議会員、神奈川県調理師試験委員(平成25年~令和4年) | |||